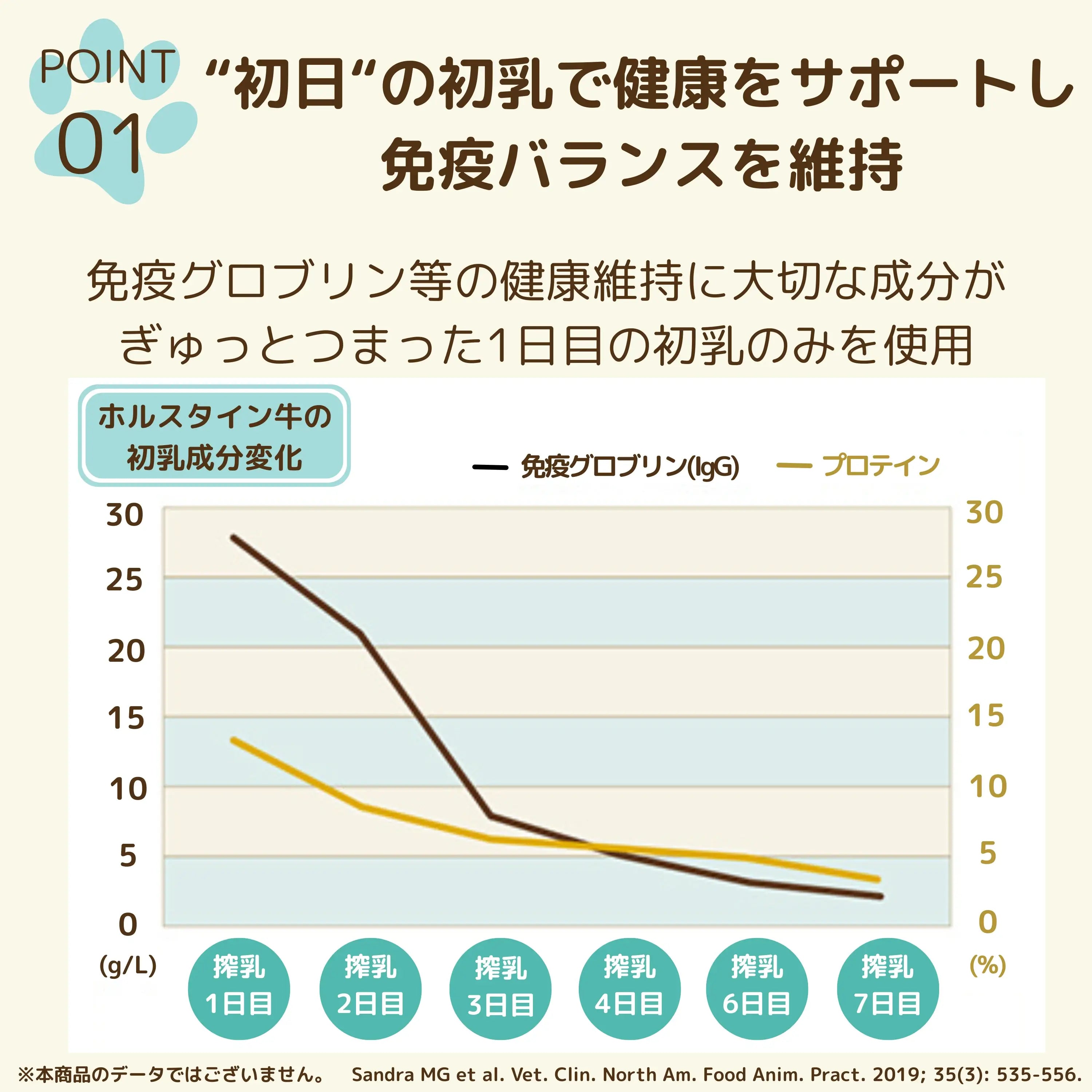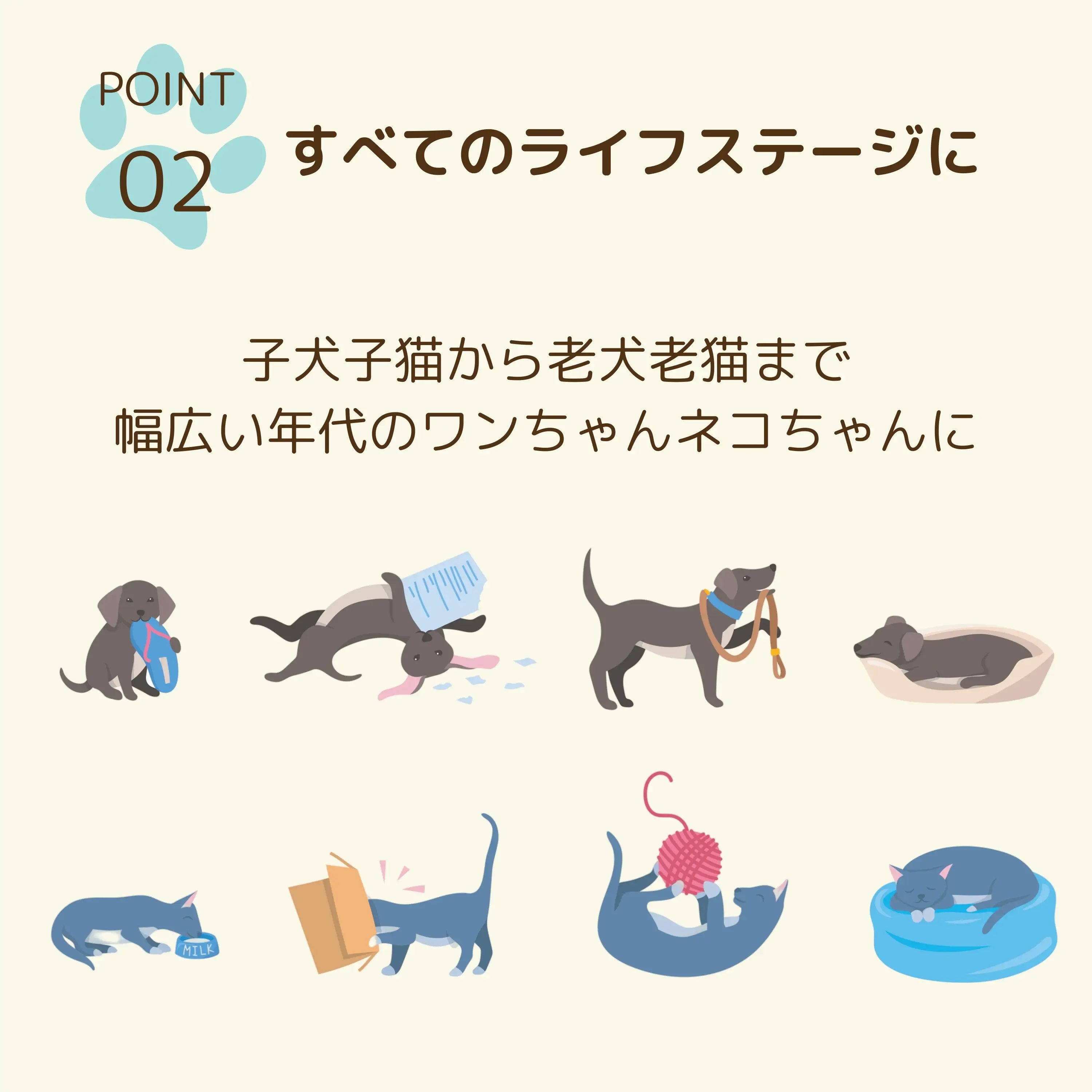L8020乳酸菌がYahoo!ニュースで紹介されました


トモに笑顔で。
SMILE TOGETHER AS ONE.
ペットとヒトが
トモに笑顔で暮らせる世界を目指して
ペットは、ヒトとトモに暮らしていく家族です。
トモに健康に、笑顔で暮らせる世界を目指して、
私たちヒューペルは、ペットのための良質なサプリメントをお届けします。
Human + Pet + Smile = HuPele
お知らせ
chevron_leftchevron_right
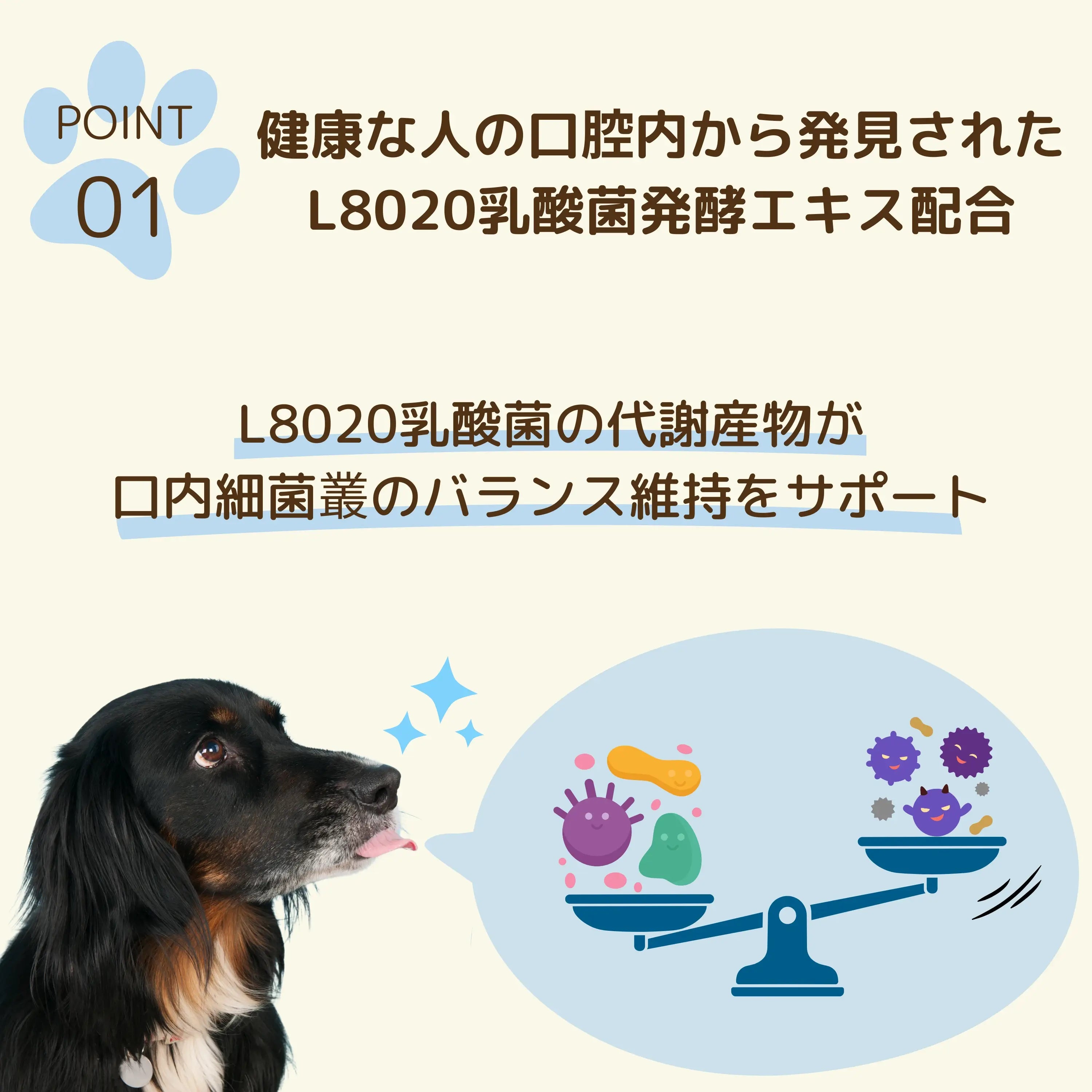
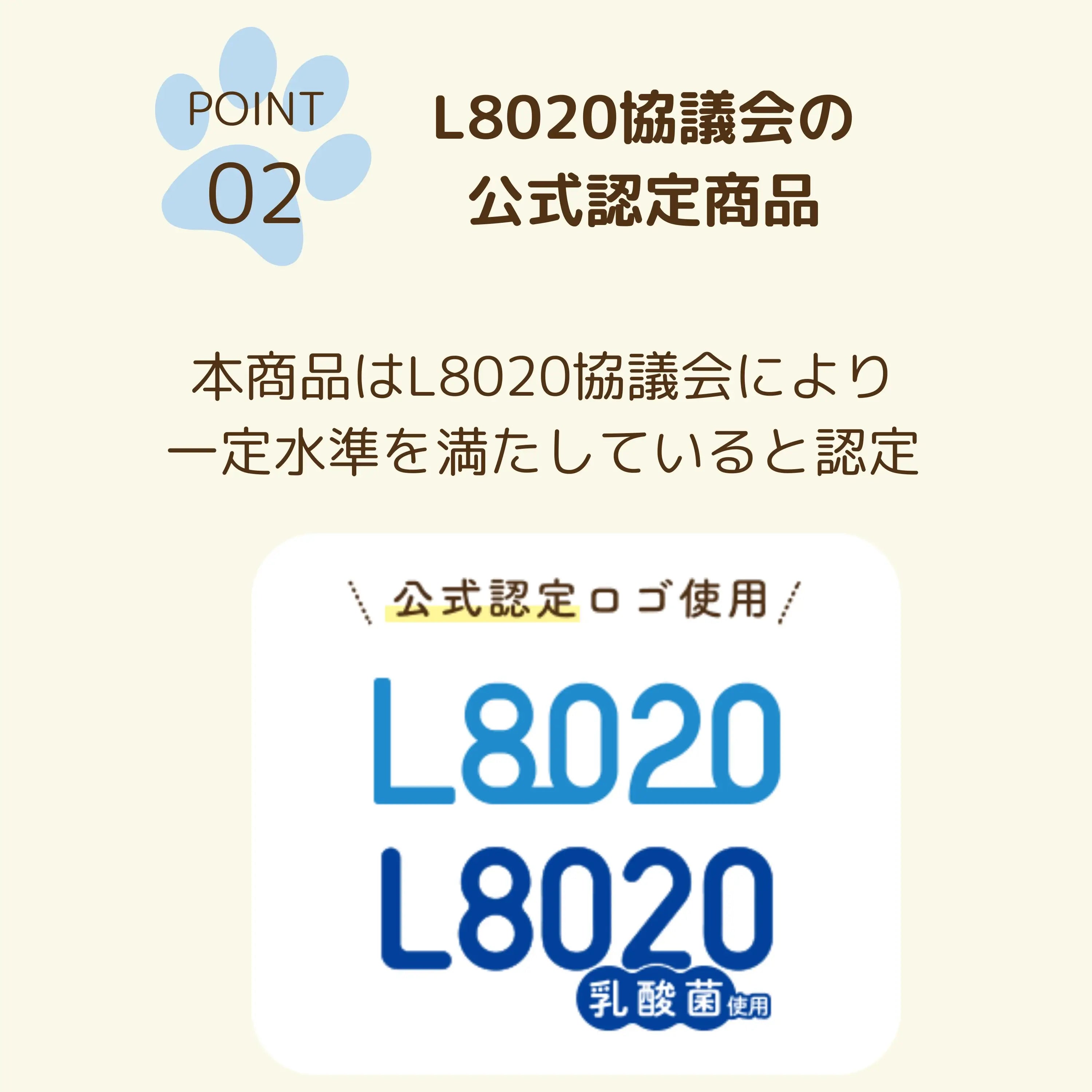
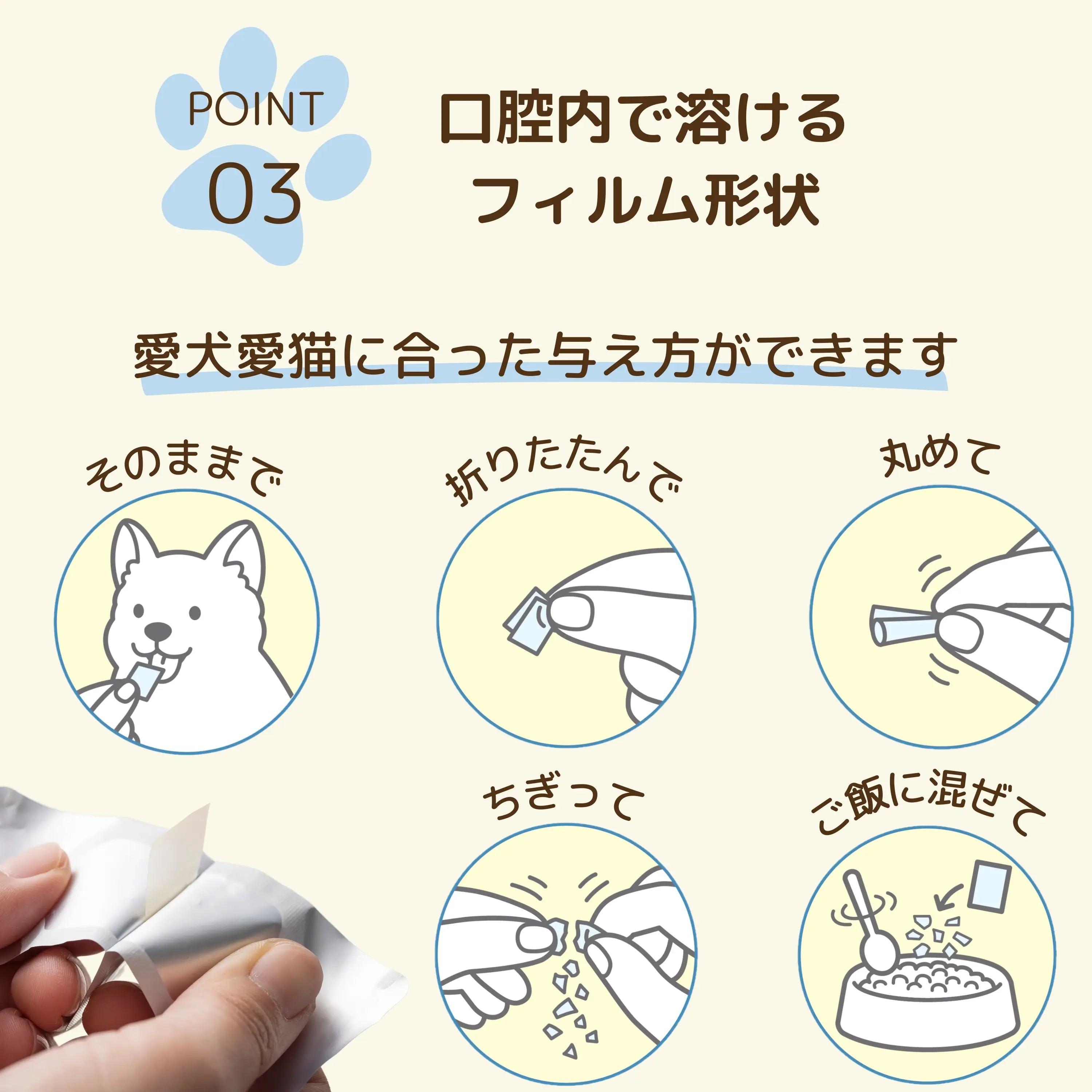
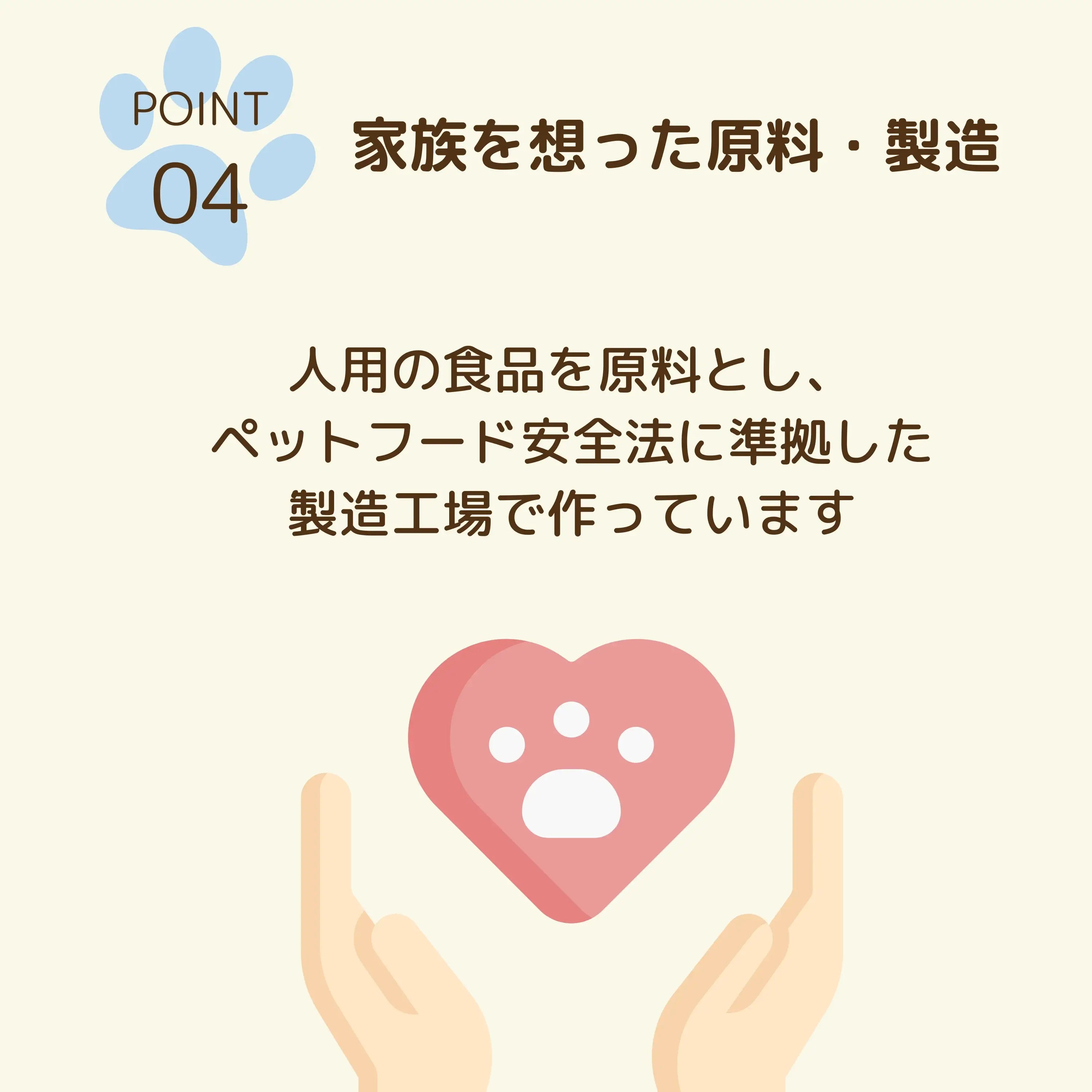
商品一覧
chevron_leftchevron_right